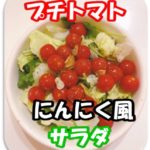にんにく栽培をした方であれば、必ずと言っていいほど経験をするであろうさび病について今日は書いていきます。
このさび病は放置しておくと、にんにく畑が大変残念な姿になってしまうのでぜひ対処して良いにんにくを作って欲しいなと思います。
今日はリクエストをいただいたので、さび病で困っている方向けに記事を書いていきます。
- さび病とはなにか
- 適切な植え付け
- 除草作業
- 葉をチェックする(大事なところ)
- 収穫時期
- サビ病の葉っぱの処分
さび病とは何か
にんにくのさび病は、にんにくの葉や茎に発生する菌の病で周りにも感染させます。葉にボツボツができてにんにくの成長に悪影響を及ぼし、きれいな大きな玉にならなくなります。
下の写真より、さび病は葉についた黄色い点のものです。

農業本では、窒素過多や近隣のねぎ畑などから伝染ると言われています。
この窒素過多が個人的に厄介だと思っていて、にんにくの畑には肥料がどうしても必要になってきます。肥料が少ないと葉が青くならず枯れてしまいますし、多いと窒素過多状態の畑になって病気になりやすくなります。(人間と一緒でバランスが大事)
そのため、肥料が少ないなと思う程度にして、追肥をするくらいがちょうどよいと感じてます。
しかもさび病が発生するのは、植付から7ヶ月くらい経って収穫時期が近いタイミングで発生するのでいやらしいです。
適切な植え付け
にんにく畑の風通しを良くし、湿度を低く保ちます。これにより、サビ病のリスクを減少させることができます。そのため植え付け間隔も広いほうが良いように思えますが。
とにかく草が勢いよく伸びる春先には植え付け間隔が広くても多湿状態にすぐ変わるため、病気が発生しやすい環境が作られてしまいます。黒マルチをして草取りをすれば、20cm以下間隔で十分かなと感じています。
除草作業
春になると少し前に除草作業しても、すぐに草が生えてきます。

にんにくはとにかく期間が長いので冬前後の除草は気をつけておかないといけません。
草があることで先程述べたように病気が発生しやすい環境が生まれ、栄養も横取りされます。
黒マルチを敷くことで作業は少し軽減できますが、除草剤なしでやろうとするとこまめに手入れをしないと気づくと草原のようになってしまいますからね。
葉をチェックする(大事なところ)
暖かくなってくると葉を小まめにチェックすることをオススメします。
葉の色が薄くなってくると肥料が足りない合図なので追肥をし、黄色点が葉っぱにつくものがあったらサビ病ですから他の作物に感染しないうちに間引けば広がりを防止できます。
だいたい3月ごろから除草作業しながらチェックすると良いかと思います。
収穫時期
季節的に愛知県では4月下旬から収穫するケースが多いです。他の農家さんもこの時期になると売り出すのでだいたいみなさんこの時期に収穫してると思います。
この時期までに蔓延してしまったサビ病のにんにくは、収穫しても玉まで影響がでていなければ食べても問題ないので食べられますし、商品にもなるので出荷します。
玉にボツボツができてしまったものは商品にならないので、それはあきらめましょう。(僕は黒にんにくにして食べてます)
国産ブランド(福地ホワイト)などは、早稲タイプのにんにくに比べて収穫がもう少し暖かくなってからが適期になるのでサビ病との戦いが長引くため難易度は高めです。
中国ブランドなど早稲は4月ごろに収穫できますが、国産ブランドは5月以降と暖かい時期を長く経験する分、草との戦いが長引き病気にもなりやすく、葉のチェックは欠かせません。
サビ病の葉っぱの処分
サビ病にかかった葉は、感染力があるので畑に捨ててはいけません。
燃やせる環境であれば燃やしたいところですが、うちでは1箇所に山盛りに積んで枯らせ、近くでサビ病の影響を受けやすいネギや玉ねぎなどは作らないようにします。
結論
サビ病で気を付けることは、黒マルチを敷いて、排水がちゃんとできていれば草が9割かなと思います。
残りの1割は周りの畑などからの影響や感染が広がる前に間引くなどですが、とにかく草を減らすことでだいたい対策はできます。にんにくの産地などへいくと結構きれいに草を削り取っている畑を見かけるので上手に対策されています。
ただ、まぁ…除草剤を使わない無農薬はやっぱ大変なんですよね。
わかります。
でも、やっぱ僕も含め多くの方が農薬が散布されていない作物を望んでいますので、やっぱその想いにも応えたいって気持ちと葛藤するんですよね。
以上、参考になれば幸いです。